環境に関する苦情処理制度
KPI
-
項目
正式な苦情処理制度に申し立てのあった環境に関連する苦情の総件数
-
2014年度実績
(連結)0件
責任部門
基本的な活動:各拠点
集約:CSR環境推進室
考え方・目標
なぜ「環境に関する苦情処理制度」が重要取り組み項目なのか
理由と背景の解説
国内外に生産拠点を持つ横浜ゴムグループは、工場から出る騒音や臭気などの悪影響をできるだけ抑え、地域住民の皆さまとコミュニケーションを取り、期待に応え続けることで信頼関係を構築していくことが、各地域で継続的に事業を行っていくために重要なことだと考えています。
環境に関する苦情処理制度は、工場周辺の地域住民の皆さまを中心に、誰でも苦情を申し立てることができる制度であり、地域住民の皆さまに対して、全力で環境整備を行うこと、さらには工場内部の環境整備にもつながる制度です。これらのことから、「環境に関する苦情処理制度」を横浜ゴムグループの重要な取り組み項目として選定しました。
苦情処理方針および考え方
環境に関する社内外の情報に対し、全社にわたる情報授受の方法を明確にし、社外の利害関係者との適切なコミュニケーションを実現するとともに、拠点間でより迅速かつ正確に情報の共有化を行うことで、全社的に類似の苦情などの再発を防止することを目的とします。
環境に関する苦情処理制度の概要
各拠点において取得した社外環境関連情報の中から、環境リスクになり得る可能性のある情報を「外部情報受付台帳」に記入し、全社要領の外部情報の基準に基づき外部苦情かどうかの認定を行います。外部苦情と認定したものには、全社要領の緊急事態の対応基準に従って処置を行うこととしています。外部苦情と認定されなかったものや、それ以外の情報については、各拠点の環境担当者が必要と判断した場合、その都度関連部門へ連絡しています。
行政から注意・指導・勧告があった場合は「外部情報受付書」を発行し、同時にCSR・環境推進室、ほかの拠点およびタイヤ・MB(工業品)それぞれの生産環境部会事務局に送付することとしています。
CSR・環境推進室では、法務部から助言を受けながら対策などに対してアドバイスを行い、全社的に協業し対応しています。
苦情処理の流れ
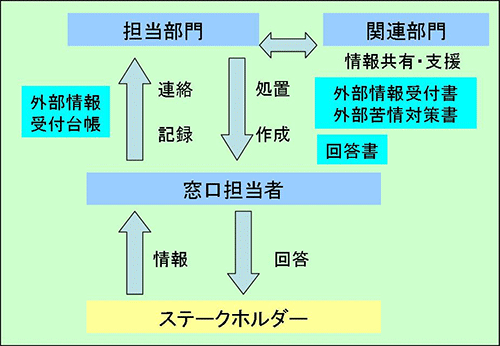
苦情が申し立てられた場合の解決プロセス
環境管理責任者が外部苦情と認定した場合、「外部苦情対策書」を発行し、CSR・環境推進室およびほかの拠点およびタイヤ・MBそれぞれの生産環境部会事務局に送付しています。
当該拠点の環境管理事務局は、一連の受付から回答までを文書にて拠点の経営責任者に報告して了承を得た後、外部の情報提供者に「回答書」で回答します。当該回答書は、ほかの拠点およびCSR・環境推進室から要求があった場合は、その都度送付し共有を図っています。
苦情処理制度利用者
すべての利害関係者が利用できます。
苦情処理制度利用の周知方法
環境に関する苦情処理制度の全社要領を策定し、国内外の全拠点へ発信しています。また、各拠点への定期的な監査を実施する際には、毎回、制度の概要や利用方法について周知徹底を図っています。あわせて各拠点内でも、環境会議などの機会を利用し、制度についての理解を深めています。
苦情処理制度の有効性についてのモニタリング
社内モニターおよび社外モニターを各拠点内で取り決め、定期的な訪問等で情報収集、コミュニケーションをとり、苦情処理制度が有効に運用されているかどうかチェックを行っています。
目指す姿(達成像)/目標
苦情に対する収集や対応はマニュアル化されており、横浜ゴムグループ全体で同一対応できる体制をとっています。引き続き、モニター制度などを活用し、制度が適切に運用されている状態を継続することを目指します。
苦情件数については、ゼロを目指しています。
目指す姿に向けた施策
各拠点との連携強化策として、定期的な監査を実施し、問題の発生リスクの高い拠点については、重点拠点と位置づけ定期フォロー、環境会議出席、改善方法指導を実施していきます。
2014年度の活動レビュー
2013年度は苦情が10件発生しましたが、2014年度は、改善効果もあり2件にとどまりました。内訳は、国内における騒音苦情1件、臭気に対する苦情が1件でした。
臭気に対する改善については、国内の2拠点で、幾つかの方式を評価した結果を受けて、脱臭装置の設置、消臭剤噴霧を行った結果、非常に大きな効果を上げました。
苦情になる要因を解析し、対策につなげることで、苦情をいただいた方への説明を丁寧に行うとともに、ご要望をお聞きし確実に対応しています。
課題と今後の改善策
苦情処理制度については、引き続き社内外への周知を徹底し、適切に運用できるようモニタリングを継続していきます。
苦情の原因の一つである臭気対策については、拠点ごとに臭いの種類・成分が異なること、人の感受性によるところが大きいことから、同一の対策が困難な状況です。苦情件数ゼロを目指すためにも、原因の分析を細かに実施し、臭い成分の除去(反応、吸着)を行うべくさらなる対策を実施していきます。
