生物多様性
KPI
-
項目
生産拠点における周辺地域生態系の生物多様性保全実施率
-
2014年度実績
(連結)46%(国内全拠点、海外2拠点)
責任部門
各拠点
※活動は事業所が行い、CSR・環境推進室は事務局として生物多様性分科会を組織し、全社方針の審議や情報共有・活動の推進を行っています。
考え方・目標
なぜ「生物多様性」が重要取り組み項目なのか
理由と背景の解説
当社は天然ゴムをはじめとする自然資本(自然の恵み)に依存して事業を営んでいます。また、多くの生産工場では、装置を冷却するために大量の水を利用し、熱・二酸化炭素を放出しています。このような事業活動によって生じる自然環境への負荷が、現在地球規模で進んでいる生物多様性の喪失と決して無関係ではないと認識しています。この自然の恵みを与えてくれる多様な生命のつながり(=生物多様性)の保全と持続可能な自然資本の利用に取り組み、未来の世代に伝えていくことが、われわれの責務であると考えています。
生物多様性ガイドライン
基本方針
私たちは、自然が生み出す恵みに依存して事業を営んでいます。この恵みを支える「多様な生命のつながり=生物多様性」が、地球規模で急速に失われていることを認識し、事業活動を通じて生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用に取り組むことで、豊かな自然を未来の世代につなぎます。
行動指針
- 経営課題としての認識
横浜ゴムは、生物資源を直接利用し、また生物多様性に影響を与える事業活動を行っていることから、自然の恵みの重要性と危機を認識し、長期的な視点で生物多様性の保全に取り組みます。 - 社員の全員参加
自然の恵みに対する社員の意識を高め、すべての社員が業務や地域社会で生物多様性保全に貢献します。 - 生物多様性への影響の把握と低減
事業活動が生物多様性に及ぼす影響を把握し、その影響を回避または最小化することに取り組みます。 - サプライチェーンを通じた生物多様性保全
生物多様性保全は、資源の採取段階における配慮が重要であることを踏まえ、サプライチェーンにおける関係者との連携を通じて、資源採取地の生物多様性保全に貢献します。 - 生物資源の持続可能な利用
生物多様性の保全に関わる知見を収集し、技術開発、設計・生産プロセスの革新や、バリューチェーンにおける生物多様性保全への取り組み等を通じて、生物資源の持続可能な利用に取り組みます。 - 情報の共有とコミュニケーション
生物多様性保全に関する情報や社会要請の把握に努め、自らの活動成果を積極的に開示し、顧客や地域社会、NGOや行政など、ステークホルダーとの対話と連携を推進します。
目指す姿(達成像)/目標
「生物多様性の保全」については、自然と共生し、環境マインドを持った従業員の育成を目指しています。そのために事業活動および社会活動を通じて活動を推進していきます。
「YOKOHAMA千年の杜」プロジェクトでは2017年までに国内外の生産拠点および関連部門の敷地内に50万本の苗木を植えることを目標にしています。
横浜ゴムの環境活動の方針
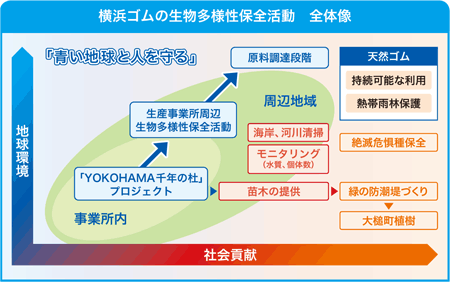
目指す姿に向けた施策
事業所のある場所は地理的、歴史的、文化的に異なる立地に位置しています。そこに生存する生き物も異なることから、事業所ごとの状況把握と課題設定が必要と考え、当社の生物多様性保全活動はステップ展開を行っています。事業所を取り巻く水域・緑地・自然保護区や住居・工場など、周辺環境を大まかに把握した後に調査した事業所のある周辺地域で、事業活動の影響のある河川などで水質の調査や出現生物のモニタリングを行い、評価対象生物を設定します。モニタリングを、年間を通して継続することにより事業活動の影響を評価し、保全する生物の対象を決定して保全活動を行ない、結果を公表しています。
水質の調査として水温・電気伝導度・pHなど、生物のモニタリングとしては野鳥観察、植生調査、水生生物や昆虫の観察を行っています。
なお、すべての国内事業所でSTEP3までの活動が完了しており、海外拠点でも順次活動を展開しています。
| 水質 | 水生生物 | 植生 | 野鳥 | 昆虫 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三重工場 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 三島工場 | ○ | ○ | |||
| 新城工場 | ○ | ○ | ○ | ||
| 尾道工場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 平塚製造所 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 茨城工場 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 長野工場 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| YTMT | ○ | ○ | ○ | ||
| YRTC | ○ | ○ | ○ |
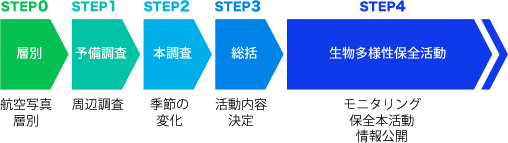
YOKOHAMA千年の杜
2014年末での植樹本数は累計36万9千本に達しました(達成率74%)。森の成長と環境の変化を評価するために、成長量の調査(樹高、胸高直径の測定)と工場敷地内に出現する野鳥の調査を行っています。苗木の成長量の調査から千年の杜の二酸化炭素の固定量を算出しており、千年の杜の二酸化炭素固定量が一般的な広葉樹林よりも多いことが分かっています。これは、多種類の樹種を混植・蜜植することの効果であると考えています。
野鳥調査では、これまでに工場敷地内で52種類の野鳥が観察されています。植樹3年目からは、森林を好むアカハラが見られるようになりました。これは、野鳥にとって千年の杜が本来の森として機能していると考えられます。また、センダイムシクイや水辺で見られるオオヨシキリが観察されており、野鳥が生息域を移動する途中で寄る中継地点として千年の杜が機能しているのではないかと考えられます。
2014年度の活動レビュー
国内工場はすべてStep4(保全活動)段階での活動に到達しました。また、海外拠点ではタイのタイヤ工場と天然ゴム加工工場でもStep4を開始しました。
サプライチェーンへの生物多様性保全活動の拡大
原料調達段階での生物多様性保全調査として、インドネシアおよびタイでの4つのタイプの天然ゴム農園(大規模プランテーション、従来型の大規模農園、従来型の小規模農園、アグロフォレストリー型農園)で生物多様性調査を行いました。その結果、大規模プランテーション農園以外では豊富な生物種が確認され、日本の里山や田園での多様性に似た環境が形成されていることが分かりました。
地域コミュニケーション
平塚製造所での施設公開イベント「第6回ThinkEcoひらつか」にて第1回生物多様性パネルディスカッションを開催しました。従業員、地域住民、環境NPO等をはじめ、多くのステークホルダー(約60名)の方に参加いただき、横浜ゴムの生物多様性に関する成果報告と今後の活動への指針の共有化が図られました。
事例紹介
三重工場
3つのチームで以下のとおり、生物多様性保全活動を継続しました。
- ノッポチーム:工場排水先河川(桧尻川・ほとす川)での水質調査とメダカなどの水生生物調査
- ブラックチーム:流下先の海岸(大湊海岸)での外来種抜根と在来植物の株数の測定、アカウミガメの産卵調査の実施
- チビッコチーム:工場の雨水調整池でのビオトープづくり、水質調査と生物調査の実施、とんぼ、水生生物調査、水質測定
また、2013年の夏期休暇中、工場排水を停止した時期に魚の大量死が発生しました。そのため2014年は、操業停止時も地下水を汲み上げて排水を行った結果、目立った魚の死骸は確認されず、工場からの排水が河川の環境保全につながっていると考えられます。伊勢市からの要請もあり、今後も長期休暇中も排水を流すことにしています。
新城工場
工場排水の流出先である野田川、黒田川での水質調査および生物調査を継続して実施。2014年は野田川ではカジカ、黒田川ではサワガニが見つかり、きれいな川であることが証明されました。四谷千枚田では休耕田のビオトープ化を行いました。
10月24日には、愛知県環境部自然環境課主催の 「『愛知目標』達成に向けた地域の役割」生物多様性自治体ネットワーク パネルディスカッション」にて、工場長の城川が新城工場での取り組みを発表しました。
三島工場
工場排水の流出先である御殿川での水質調査および生物調査を実施。工場排水口の上流部よりも下流部の方が、電気伝導度(EC)が低いことが確認され、工場排水が水質の良化に貢献していることが確認されました。
長野工場
長野工場は、他工場に比べて自然度の高い地域に位置する工場です。雨水以外の排水がほとんどなく、横浜ゴムの他の工場と比べて環境影響度の低い工場であると考えています。長野工場での生物多様性保全活動は、地域貢献と従業員教育という側面に重点が置かれています。昨年のモニタリングでは長野県の準絶滅危惧種のアカザや絶滅危惧I類のシャジクモが見つかりました。
茨城工場
工場の排水先である園部川での水質調査と生物調査を実施しました。生物調査は植生、水生生物、鳥類の調査を行っています。園部川は農業用水として利用されていることから排水の水質について十分に注意を払っています。工場排水先は上流部に比べて電気伝導度が低く、透視度が上がっていることから、工場排水は十分な管理ができていると考えています。水生生物調査では、茨城県の準絶滅危惧種のコオイムシが確認されています。
YTMT
タイのタイヤ工場であるYTMTは、工業団地内に立地しています。日本の工場と異なり、工業団地が取水および排水を一括管理していることから、工場単独での取水・排水域への影響は確認できていません。そこで、敷地内の緑地(千年の杜やビオトープ)を評価するための鳥類、昆虫類のモニタリングを実施しています。地域の生物の生息域の確保するとともにこの活動を通じて、従業員の環境教育も行っています。
YTRC
YTRCは、タイのスラタニ県にある横浜ゴムグループで唯一の天然ゴムの加工工場です。天然ゴムの加工工程では大量の水を利用しますが、100%リサイクルすることで水資源の有効活用に努めています。また敷地内の遊水地は、隣接するタッピー川のワンド※としての役割を果たしていることが調査の結果から分かりました。そこで、水生生物(魚類)と水質のモニタリングを2014年11月から定期的に行っています。今後は、地域の生態系の保全のために、その調査結果を確認とともに近隣住民の皆さまと対話を進めていきたいと考えています。
※ワンド:川の本流と繋がっているが、河川構造物などに囲まれて池のようになっている地形のこと。魚類などの水生生物に安定したすみ処を与えるとともに、さまざまな植生が繁殖する場ともなっています。
課題と今後の改善策
これまでは、横浜ゴムグループの事業活動の影響を受ける地域に生息する生物種の把握を中心に活動してきました。今後は海外拠点への展開と、各事業の地域の生物多様性保全の維持・改善を行い、持続的な操業につなげていきます。
生物多様性は一般の人にとってはまだなじみのない概念であるため、モニタリング活動や保全活動への参加によって、従業員に生物多様性保全の大切さへの理解を深めていくことと、地域への情報発信を積極的に行うことによって当社の取り組みを理解していただく活動を進めていきます。

